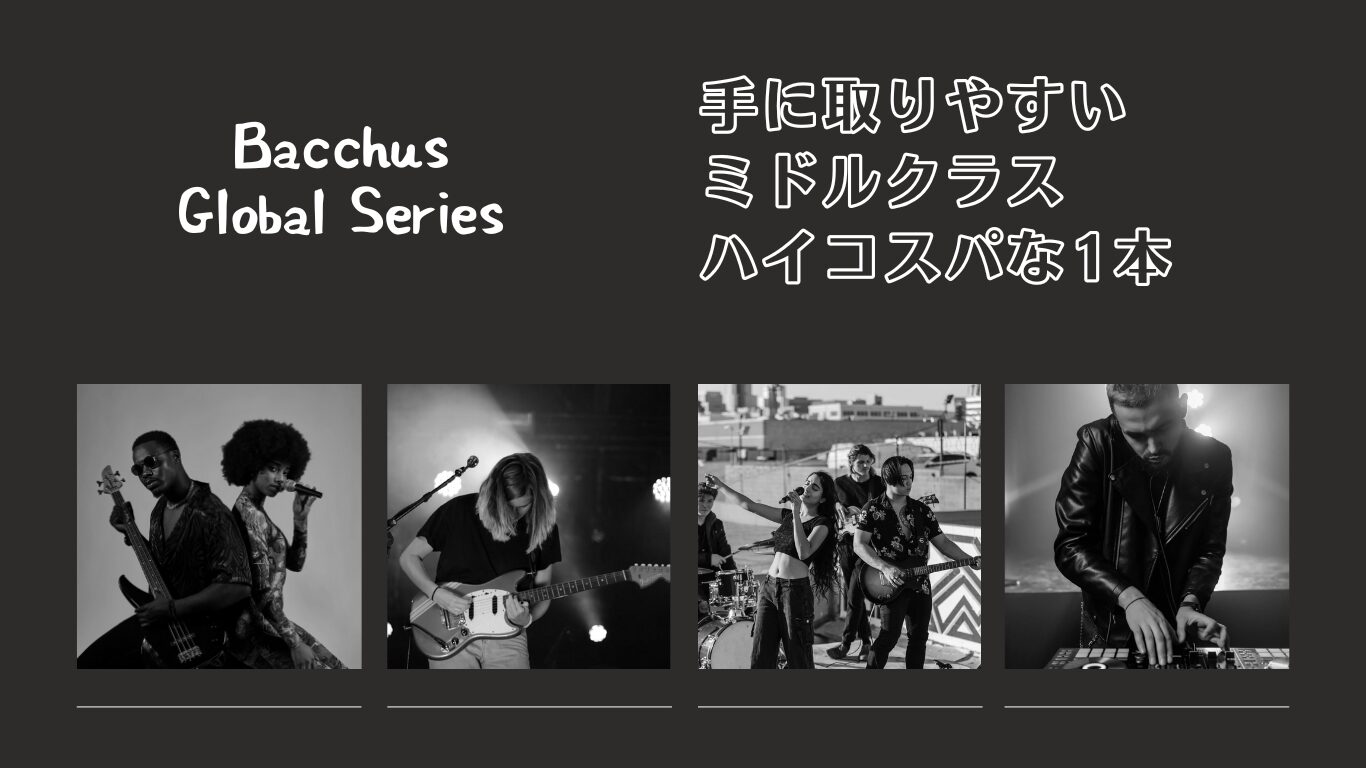【解説】ハイエンドのベースはなぜ高い? | 楽器に対して一切の妥協がない | 材の品質 人件費 工程 工数 調整

10万円と40万円のベースはなにが違う?
ベースは価格帯は本当に様々ですよね。
- 木材
- 電装系(+ペグ&ブリッジ etc…)
- 人件費
コレらを総合してベースの販売価格が決められる訳です。
Fenderの楽器を例に持ってきましょうか。
10万円で買えるFenderのベースですとプレイヤーシリーズが代表的ですね。
【Fender / Player II Jazz Bass】
こんな感じのベース――通称フェンダーメキシコの1本。
一方で40万円のハイエンドベースだとアメリカンヴィンテージが候補に挙がります。
【Fender / American Vintage II 1966 Jazz Bass】
最強クラスのパッシブベースだと思いますね。
そんな両機の仕様を軽く比較してみましょうか。
こんな感じ。
| Fender American Vintage II 1966 Jazz Bass | Fender Player Ⅱ Jazz Bass |
|---|---|
| 市場価格 / 396000円~ | 市場価格 / 104000円~ |
| Body Wood / Alder | Body Wood / Alder |
| Neck Wood / Maple | Neck Wood / Maple |
| Fingerboard / Round-Laminated Rosewood, 7.25 (184.1 mm) | Fingerboard / Maple or Slab Rosewood |
| Pickups / Pure Vintage ‘66 Single-Coil Jazz Bass (Bridge, Middle) | Pickups / Player Series Alnico 5 Single-Coil Jazz Bass® |
| Controls / 2Volume 1Tone | Controls / 2Volume 1Tone |
| 生産国 / USA | 生産国 / メキシコ |
アルダーボディ、メイプルネック、ローズウッド指板――木材は一致していますよね。
では、なぜここまで価格に差が出るのでしょうか?
僕の意見としては、
- 同じ銘柄の材でも品質が全然違う
- 品質を活かす為の工程にも力が入っている(シーズニングなど)
- 1本の制作に掛ける工数が違う
- 楽器の調整に余念がない
- 人件費(人の手)が多く入っている
こういった数々の要素だと思います。
(企業秘密な部分も多く正確な情報は不明です)
僕なりに分かっている範囲の情報を丁寧にまとめてみました。
僕と一緒に勉強して貰えると嬉しいです。
ではでは、本編へどうぞっ!!
同じ名前の材でも品質が違う
先ほど木材でアルダーボディ、メイプルネック、ローズウッド指板とご紹介をしました。
確かに文面で見る仕様は一緒なのです。
ですが、当然ながら10万円のベースと40万円のベースでは木材のグレードが違います。
同じアルダーでも厳選された極上の部分をこだわって使う――ソレがハイエンド。
シーズニング(乾燥)を徹底して長期間行うことで水分量の狂いが少ない状態を維持できる。
製造の回転率が重視される価格帯では長期間の確保をすることが経済的に難しいのです。
こういった事情が絡んで、
同じ材質でもクオリティに大きな差がある

という状況が生まれます。
ボディ材に限らずネックや指板も言わずもがなですね。
こういった部分が価格相応に違うと言えるでしょう。
電装系(ペグ&ブリッジ)も同様に品質が違う
ココも言うまでもないですね。
ジャズベで言うシングルコイルピックアップ1つにしても明確に品質が違います。
ベースの中でもっとも音に影響がある部分はピックアップという意見もありますね。
形や見た目は同じピックアップでも内容やクオリティに大きな違いがあるでしょう。
| Fender American Vintage II 1966 Jazz Bass | Fender Player Ⅱ Jazz Bass |
|---|---|
| Pickups / Pure Vintage ‘66 Single-Coil Jazz Bass (Bridge, Middle) | Pickups / Player Series Alnico 5 Single-Coil Jazz Bass® |
1966年のヴィンテージスタイルを徹底追求したアメビン。
汎用性と量産性を求めたプレイヤーシリーズ。
違いが出て当然ですよね。
各種電装系やペグにブリッジも同様です。
1966年のFender過渡期を象徴するバインディング+ドットインレイ+パドルペグ等々。
外観的にも明確な違いがあります。
やっぱり価格帯相応に完成度の違いはあると思いますよ。
1本のベースに対する工数が圧倒的に多い
40万円のベースにはその1本に対して掛けられる人件費が多いという特徴がありますよね。
楽器が持つパフォーマンスを最大限に発揮できるように多くの工数を掛けられます。
木材の状態から切り出して加工して丁寧に組み込んで――。
そういった工程を一切の妥協なく行うことができる訳です。
ココが10万円の楽器だと削る(妥協する)という部分がどうしても出てきてしまう。
コストという側面を考えた時に絶対的に不可能な部分は出てきてしまうのです。
お値段が違うというのはこういった現実を生みます。
だからこそエントリーモデルという呼称からハイエンドという表現まである訳ですよ。
価格帯に合わせて取捨選択をすること。
どんな楽器で自分は満足できるのか?
納得した上で選ぶのが良いと思いますよ。
調整に余念が無い
楽器が完成した後の話でもハイエンドのベースには妥協がありません。
フレットの角の削りからネックのコンディションに演奏性の確認作業。
各社、厳格な審査の上で出荷していることでしょう。
ハイエンドベースは言い方を変えれば自社の顔みたいなものですからね。
(フラッグシップモデルとも言いますね)
半端な製品を出そうものなら自社の顔に泥を塗るも同義。
僕もBacchusのフラッグシップモデルであるBacchus Handmade Series 02 Woodline 4stを所持しています。
ハンドメイドシリーズらしく丁寧で素晴らしい作りです。

人の手が入って調整が行き届いた製品は買った後でも細かく微調整ができるもの。
末永く使える――ワンオーナーとして一生使っても良いベースになることが多いです。
色々と悩みつつ良い1本をご自分で見つけてみて下さいね。
個人的なオススメとして、
- Fender / Fender Custom Shop
- Sadowsky
- Xotic
- Atelier Z
- dragonfly
- Freedom Custom Guitar Research
- Momose / Bacchus
- Moon
- Sugi
Fender・Sadowsky・Xoticは例外として国産マシマシと言ったセレクションですね。
(Xoticは日本人の方がLAで展開するブランドなので半国産とも言えるかも??)
他にも良いハイエンドブランドはたくさんあります。
是非、参考にしてみて下さいな。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は「ハイエンドベースはなぜ高い?」というテーマで記事を書いてみました。
お値段に従ってしっかり違いはあるものです。
- 同じ銘柄の材でも品質が全然違う
- 品質を活かす為の工程にも力が入っている(シーズニングなど)
- 1本の制作に掛ける工数が違う
- 楽器の調整に余念がない
- 人件費(人の手)が多く入っている
やっぱりハイエンドにはハイエンドにしかない良さがあるものです。
副次的な効果として、
凄いベースを買っちゃった!!

という自己肯定感が上がるというメリットもありますね。
ベースを頑張ろうという気持ちを持ち上げてくれますよ。
一生モノの1本を真剣に検討している。
そんな方の役に立つ情報であったなら嬉しく思います。
「このモデル、気になるかも……」と思った方は、ぜひオンラインストアでじっくりチェックしてみて下さい。
スペックや価格、在庫状況まで、実店舗よりも確実に情報が揃っていますし、タイミングによっては限定キャンペーンもあるかもです。
▼イケベ楽器▼
イケベ楽器 / オンラインストア公式サイト
▼イシバシ楽器▼
イシバシ楽器 / 公式サイト
良い1本との出会いがありますように。
ご精読ありがとうございましたっ。
ではではー!!