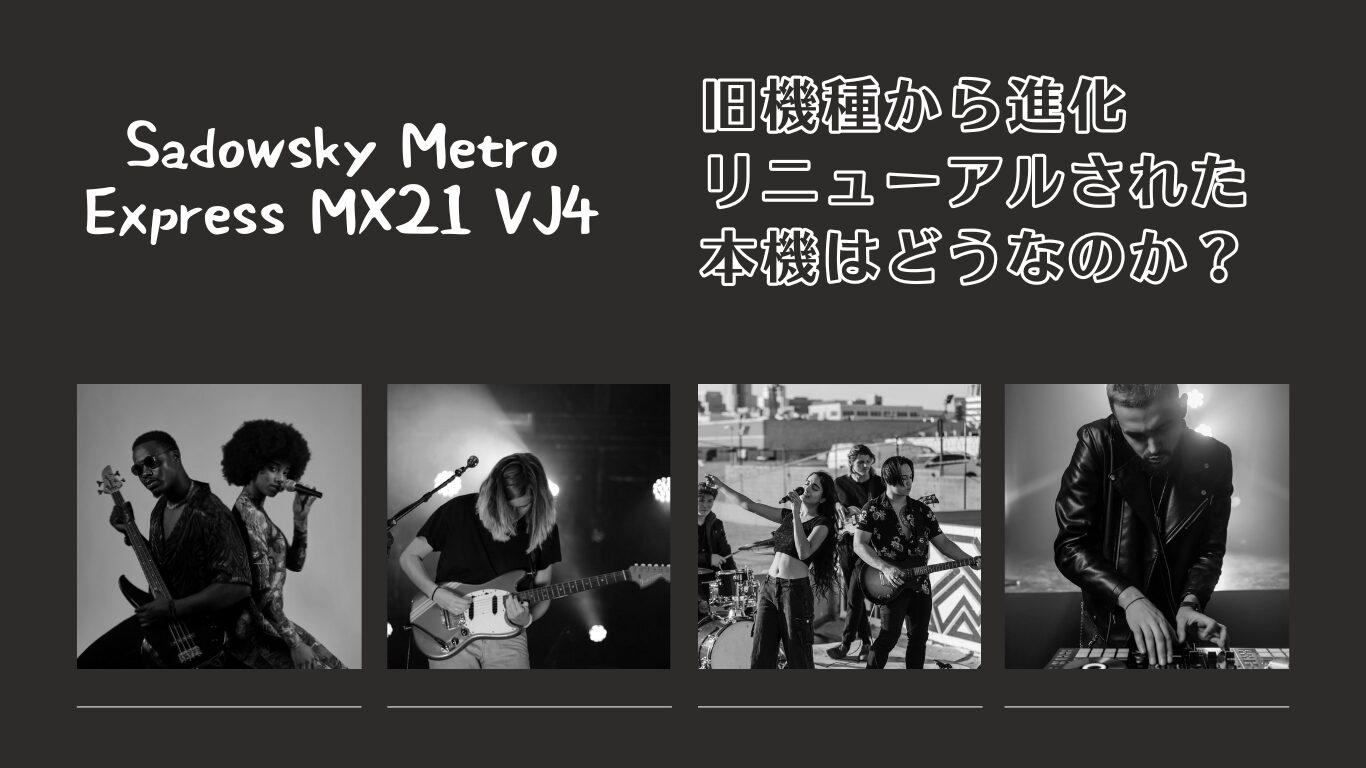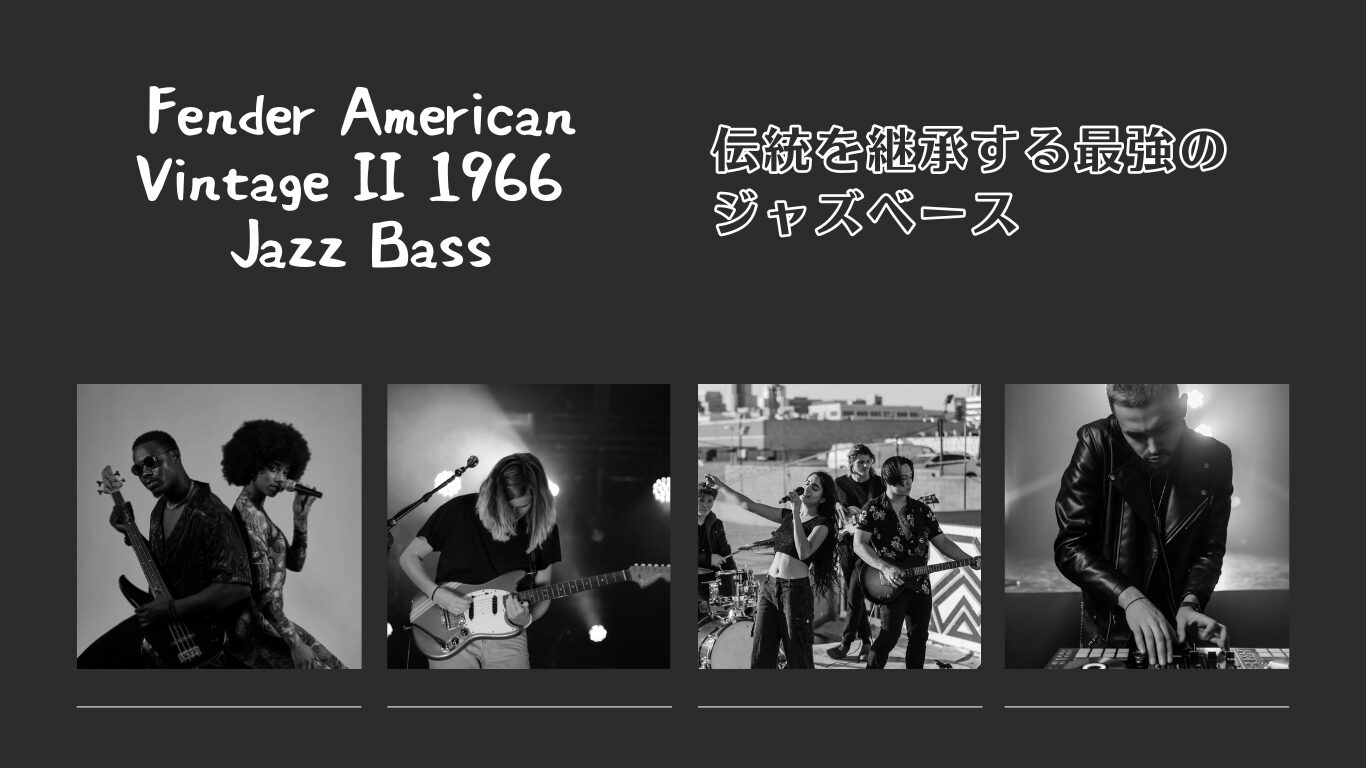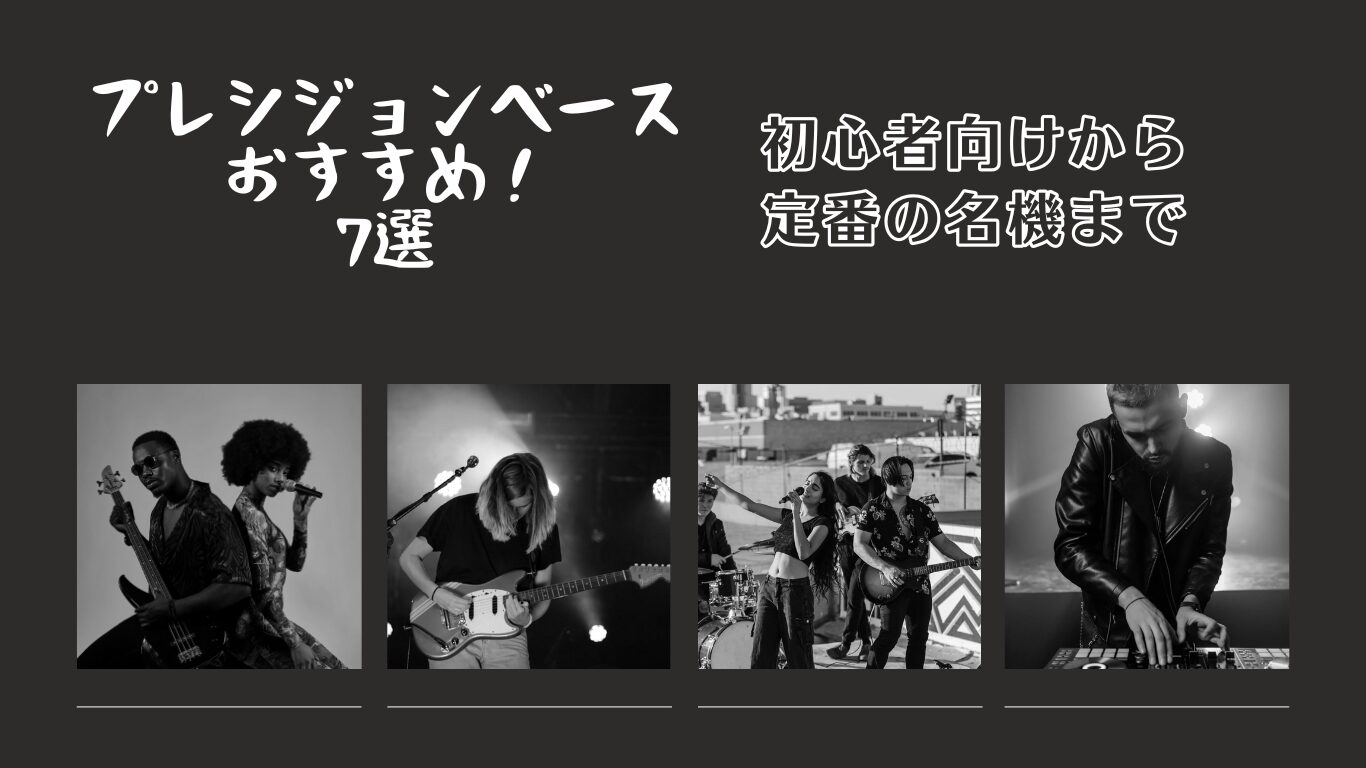【解説】バスウッドを使ったベースは? | 基本的にはコスパモデルの採用が多い

バスウッド=悪い材ではない
僕の個人的な感想として「バスウッドは悪い材ではない」という印象です。
具体的には、
① 安価なベースのボディ材として採用が多い
② エフェクターの乗りが良い
③ 腰高なサウンドの傾向がある
①の要素が原因で悪い印象を持っている方も少なくないでしょう。
僕が持っているFender Japan PB62もバスウッドのボディです。

PB62も当時はエントリーモデルとして販売されていたジャパン・ヴィンテージですね。
現行の製品だと、
【Legend / LJB-Z】
こういったエントリー価格帯の製品に採用されていますね。
なので、
バスウッドって悪い材……??

こういった印象がどうしても強くなってしまいます。
ただ、
エフェクターの乗りが良く腰高なのでスラップ等の抜けが良い

僕はこの印象を使っている身として持っています。
詳しくは、

↑の記事でも詳しく解説してあるのでご覧下さいね。
今回は、
バスウッドを採用したベースは??(特徴 / 価格)

こういったテーマで解説をしてみようと思います。
傾向や特色。
どういった意図で採用がされるのか??
僕の知見を生かして丁寧に解説して行きますね。
では、本編へどうぞーっ。
圧倒的なコストカットに繋がる
悪い材ではないという前提で木材としては加工がしやすく安価であるという点が魅力です。
なので、
採用 = 価格を下げられる

こういった事実は確かにあります。
具体的には、
【Sterling by MUSICMAN / S.U.B. Series Ray4】
このStingRayの廉価版などに採用されています。
本家のStingRayは46万円。
この差は各種の作り込みや木材の観点から生まれるものですよ。
【MUSICMAN / StingRay Special 1H】
なので「バスウッド=安い」という事実は間違いではありません。
46万円と6万円の差は驚異的と言えますよね。
実際、Ray4に関しては価格とサウンドのクオリティが非常に良い印象です。
詳しくは、
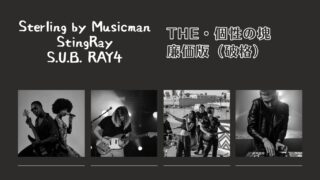
コチラの記事でもご紹介していますので興味がある方は是非どうぞ。
安くて良いものが買える。
コスパに優れているという点がバスウッドの魅力の1つですね。
実はベース向きじゃない??
バスウッドは音のバランスが良いもののやや低音が弱い傾向があります。
腰高なサウンドの特徴はココから来ている訳ですね。
なので、
決してベースに向いた材という訳ではない

コレは事実としてあるでしょう。
ロー感が薄い点はベースとして良い点には働きづらいです。
しかし、
エフェクターの乗りが良い
このフラットな特性を活かして弱点を補うことも十分に可能です。
プリアンプ等で全体を整えつつサウンドを作って行けば「抜けが良いベースサウンド」も可能になるでしょう。
腰高な点はベースの役割にこそやや不適格ですが音抜けに関しては良い側面です。
バンドアンサンブルでスラップ等をした時にもしっかり抜ける印象がありますね。
(PCのDTM上でミックスをする際にもPB62は良く鳴りますし良く抜けます)
扱い次第でどうとでもなります。
ご自分でバスウッドのベースを使っている場合はEQで補うという使い方も考慮してみて下さい。
過剰な増減は基本的に非推奨ですが適度な範囲ならエフェクターは優秀です。
採用してみて下さいな。
バスウッドを意図的に採用したベースは??
コスパを維持しつつクオリティを上げるという意味で採用したケースはあります。
FenderのMade in Japanから展開されるHama Okamoto Precision Bass #4ですね。
バスウッドボディを採用しつつ、
① パドルペグ
② ブリッジカバー
③ フィンガーレスト
こういったヴィンテージライクな側面をしっかり再現したベースになっています。
ルックスもヴィンテージのプレベっぽいですよね。
このベースの場合は「コスパを維持しつつ良いベースを作る」というコンセプトがしっかり見て取れます。
こういった採用の仕方はアリだと思いますよ。
バスウッドは必ずしも悪いものではありません。
特性を理解して使えば十二分に使い続けることも可能です。
この価格帯でもバスウッドが使われることもある――という1つの指標にはなるでしょう。
余談ですが、
ヴィンテージ楽器の(表記上は)アルダー材が実はバスウッドだった

こんな話もあったりします。
そういった側面も含めて必ずしもバスウッドは悪しきに非ずと言ったところ。
結局は弾き手次第と言った感じです。
ビリー・シーン(MR.BIG)の言葉に、
いい音楽はいい。それが全てだよ。
あまり細かい部分は考えすぎず楽しむ――良い音楽を追求するようにすると良いでしょう。
究極的に、
アルダーだろうがバスウッドだろうが良い音が出るならなんでも良い

この良い音は主観的――要するに奏者のご自身が良いと思う音で良いかと。
あるいは聴き手が良いと判断すればOKです。
価値(価格)に囚われずグッドなサウンドを追求してみて下さいね。
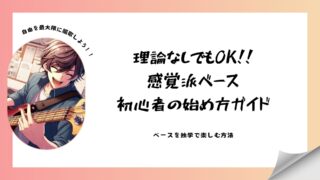
まとめ
いかがでしょうか?
今回は「バスウッドを使ったベースは?」というテーマで記事を書いてみました。
基本的には低~中価格帯のベースで採用されることが多い印象です。
しかし、
① 腰高で抜けが良い
② フラットでエフェクターの乗りが良い
この特徴を活かしてバリバリと使って行くことは十二分に可能だと僕は思います。
バスウッドだからダメという訳ではありませんね。
ご自分に合わないなーっと使う中で感じたなら乗り換えるのも手でしょう。
価格を抜きにしてリアルな使用感の中で使うか変えるかを選んでみて下さいね。
参考にどうぞーッ。
ご精読ありがとうございましたっ。
ではではー!!








.jpg)