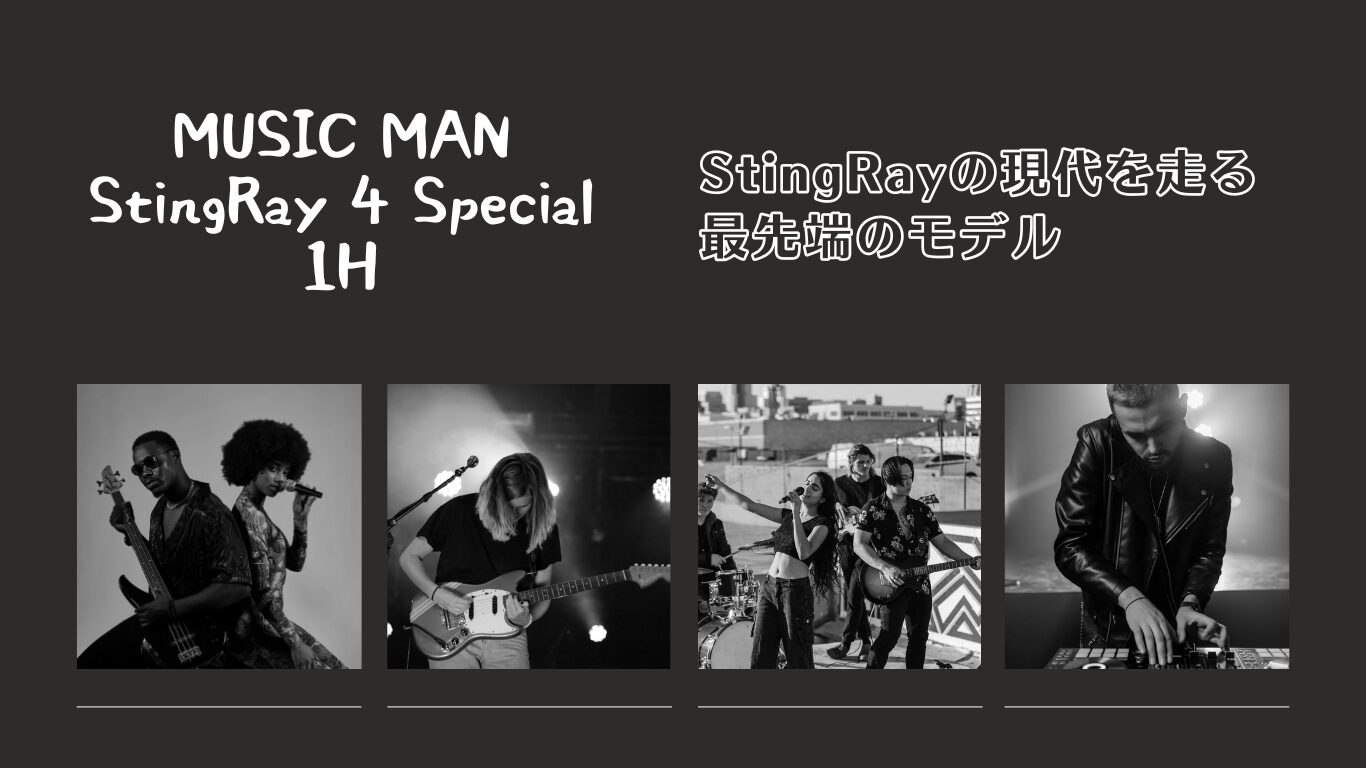【解説】Fenderのヴィンテージジャズベースの特徴 | なにが凄い??

Fender Jazz Bass:ヴィンテージの系譜と美学
Fenderのジャズベース(Jazz Bass)は1960年の登場から時代と共に仕様を変えてココまで来ています。
個人的には「エレクトリックベースの原点にして完成形」という印象ですね。
一口にFenderの(ヴィンテージ)ジャズベースと言っても実は年代ごとに特徴は様々。
マニアックに解説しつつ一緒に勉強をして行きましょう!!
1960〜1962年:誕生とスタックノブの時代
Fenderのジャズベースが史上初めて登場した歴史的瞬間ですね。
ガチのこの頃のヴィンテージを購入しようとすると300万円以上はするでしょう。
【Fender Custom Shop / 1961 Jazz Bass】
当時の仕様を再現したカスタムショップの名機がコチラですね。
(カスタムショップ製でも100万近いんですよ……笑)
特徴として、
- コントロール部:スタックノブ仕様(各ピックアップに独立したボリューム&トーン)
- ピックアップ:2基のシングルコイル。ノイズ対策として画期的な設計
- フィンガーレスト:ネック側上部に設置(親指を置く位置)
- ネック:スラブ貼りローズウッド指板、メイプルネック
- ボディ材:アルダー
- サウンド:倍音豊かで、ウォームかつ立体的なトーン
- その他:弦ミュート機構が標準装備。コントラバス的なニュアンスを意識
こんな感じですかね。
この、
その他:弦ミュート機構が標準装備。コントラバス的なニュアンスを意識
コレはブリッジのカバー内にスポンジミュートが標準装備という代物。
(当時はウッドベース的なニュアンスが求められていたので)
スタックノブ(2ノブ / 4コントロール)も含めて後の世ではなくなっていく仕様です。
また、
この時代は他の指を固定して親指で弦を弾いていた(らしい)

こういった事情からフィンガーレストも1弦側に付いていますね。
今の時代だと「どうして??」となるでしょう 笑
木材に関しては今も王道のアルダーボディ+ローズウッド指板(ハカランダ)+メイプルネックという構成。
この頃は木材も潤沢だったので質が良かったのでしょうね。
そういった意味でもヴィンテージの価値の高さはあると思います。
(+αで希少価値も乗っているので価格は圧倒的に不釣り合いですが)
深みのある風格の宿ったサウンド――と、言って良いでしょう。
1962〜1964年:黄金期と3ノブ仕様の確立
この頃がある意味ではFender Jazz Bass(及び楽器全般)の黄金期と言えるでしょう。
この頃を境に仕様の変更と共にジャズベースは完成へ向かって行きました。
【Fender Custom Shop / 1963 Jazz Bass】
内容として、
- コントロール部:2ボリューム+マスタートーンの3ノブ仕様に変更
- 指板:ラウンド貼りへ移行(木材使用量の最適化)
- カラー展開:3トーンサンバーストが主流。Sonic Blueなども登場
- ピックガード:べっ甲柄が定番。ホワイトやミントも徐々に採用
- サウンド:よりまとまりのある音像。ジャンル横断的に支持を獲得
加えて1960年初頭にあった弦ミュート機構は1963年頃を境に非搭載に。
コントロール部は現在の標準である2ボリューム1トーンになっていますね。
サウンドの傾向としては中低域が豊かで音に厚みと丸みがあると言った感じに。
僕的には「Fenderが目指すジャズベースの完成形」はこの時代ではないか――と、思っていますね。
ココからFenderはある種の迷走期(語弊があるかな?)に入りつつあります。
オールジャンルで強い最強のジャズベはこの頃ではないでしょうか??
1965〜1969年:CBS買収と仕様の変化
この頃(1965年)には創業者であるレオ・フェンダー氏が健康上の問題と経営への不安からFender社をCBSという企業に売却します。
【Fender USA / American Vintage II 1966 Jazz Bass】
1965年からの特徴として、
- 企業背景:CBSによる買収。大量生産体制へ
- 指板材:ローズウッド中心だが、メイプル指板モデルも登場
- 装飾:バインディングやブロックインレイが一部モデルに採用
- ピックアップ位置:60年代後半から微妙にブリッジ寄りへ
- ネックジョイント:基本は4点留め。マイクロティルトは未搭載
- ロゴ:トランジションロゴ(やや丸みのある書体)
企業背景の中にある「CBSによる大量生産体制」――コレが1つの問題だった。
今でもヴィンテージの価格がこの頃を境に下落し始めているように「生産性重視=品質が悪化した」という解釈も多いのです。
バインディングやブロックインレイが採用されるなど外見への注力もありましたね。
全体のイメージとして「変化への予兆を持った1970年代と1960年代の中間」というイメージを持っています。
この頃のFenderは品質は保っていた――と、僕は思います。
作り自体も1970年代後半に比べると全然良いでしょう。
1970〜1976年:70’s仕様の確立と個性の分岐
僕的にはルックスの傾向やサウンドの性質自体はこの頃をモチーフにしたベースが好き。
イメージとしてはこんな感じのリイシューモデルとかでしょうか。
【Fender / Made in Japan Traditional 70’s Jazz Bass】
ただし、この頃(特に1970年代後半)は特に製品の質が粗いことも多かったそう。
今でも当時のヴィンテージの価格が控えめなのはこういった理由が大きいでしょうか。
70年代の特徴として、
- ボディ材:アッシュ材が主流に(より硬質な音像)
- 指板材:メイプル指板+塗装仕上げが増加
- ピックアップ位置:ブリッジ寄りに約1cm移動 → タイトなサウンド傾向
- ネックジョイント:1974年以降は3点留め+マイクロティルト搭載
- 装飾:バインディング+ブロックインレイが定番化
- ロゴ:モダンロゴ(太字で直線的なデザイン)
- トラスロッド:ヘッド側に調整口(ブレッドナット)
この頃からボディ材にアッシュと指板にもメイプルが使われ始めますね。
リアピックアップの位置も全体的にブリッジ寄りに配置されることで「硬質な音」と言われることも多いです。
木材の傾向も相まってより一層にその印象が強いですかね。
ネックジョイント部分は3点止めとマイクロティルト搭載(ネックの仕込み角度を調整可)
ただし、このマイクロティルトは「ハイ起きがしやすい」とも言われる曰く付きの仕様。
また、ヘッド側にトラスロッドの調整口がある機構もこの時期特有でしょうか。
コイツも悪名の1つとも言われており「指板が割れる」という要因でもあるそう。
いやぁ、全体的にこの頃は、
(特に1970年後期は)CBS買収後の顕著な悪化が見られる時期でもある

僕としてはサウンドのアプローチとして結構好きなんですけどね 笑
実際、マーカス・ミラー氏が使っているベースもFenderの1977 Jazz Bassですし。
ただし、マーカスのベースはロジャー・サドウスキー氏の手によってゴリッゴリの魔改造が施されています。
分かっているだけで、
| 改造項目 | 内容 |
|---|---|
| アクティブプリアンプの搭載 | Bartolini TCT(3バンドEQ:Bass / Mid / Treble)を内蔵。高域の煌びやかさ、中域の存在感、低域のパンチ感を強化。スラップ奏法に最適化。 |
| ノイズ除去・シールディング強化 | CBS期Fender特有のノイズ問題を解消するため、内部配線の見直しと導電塗料によるシールディング処理を実施。 |
| フレット・指板の修正 | ネックの安定性と演奏性を高めるため、リフレットと指板の平滑化を実施。低弦高でもビビらないセッティングが可能に。 |
| ブリッジ交換 | サスティーンと安定性を向上させるため、Badass IIブリッジに交換。マーカスサウンドの物理的基盤に。 |
| ピックアップの調整・交換 | フェンダー純正PUの出力バランスや高さを調整。Bartolini製PUとの組み合わせも一部で検討されたが、本人の個体は純正ベースの調整が有力。 |
ほぼ原型を留めていませんね 笑
今でも改造や調整を加えて1970年のジャズベースを使っている方は居るはず。
結構大胆なアプローチを入れているユーザーも少なくないです。
Suspended 4th 97.9Hz Bass Playthrough
プロベーシストであるサスフォーのむうさんも(昔使っていた)1972年のJazz Bassはオーバーホール的なメンテナンスが入っているらしいです。
(【機材紹介】Suspended 4thのベーシストが使ってる機材が知りたい!によればマイク・ルル氏のメンテが入っているそうですよ)
現在のFenderでも、
1970年代をモチーフにしたベースが極端に少ない!!

カスタムショップ製ですら70年代はめったに作られないですからね。
60年代と70年代には温度差という意味で大きな差がある。
善し悪しは別としてコレは事実ではないでしょうか??
(僕は70’s Jazz Bassのサウンドが好みですよ)
まとめ
いかがでしょうか?
今回は「Fenderのヴィンテージジャズベースの特徴」というテーマで記事を書いてみました。
ヴィンテージベースには、
経年劣化によって倍音や中低音域の密度が増す

こういった(主観的な)解釈があるのですが――必ずしも〝そう〟とは限らないので最後の補足としておきます。
(木材が枯れて乾燥したことで振動伝達がスムーズになるのだとか)
1つの要素として付加しつつ年代ごとの性質を合わせるとヴィンテージの価値が明確になるのではないでしょうか??
個人的には、
- ルックスや音の個性なら70年代が好き
- オールラウンド的な完成度は圧倒的に1962年から1965年前期頃が強い
こんな解釈でベースに対して向き合っています。
最終的には「好み」――コレ1択が結論ですよ。
是非、好きなベースを探してみて下さいね。
ご精読ありがとうございましたっ。
ではではー!!